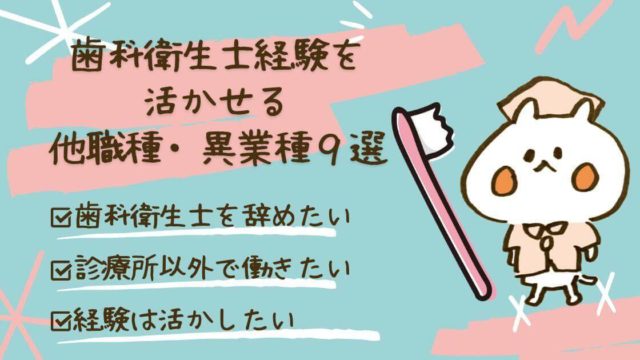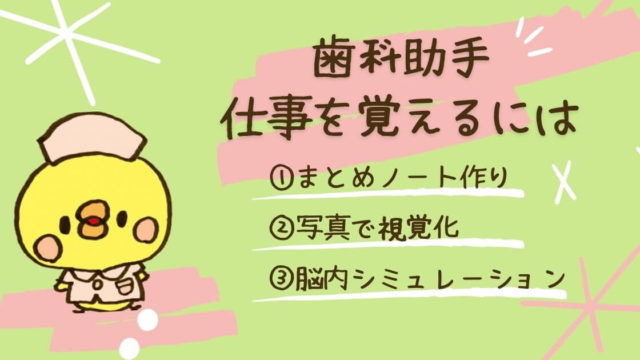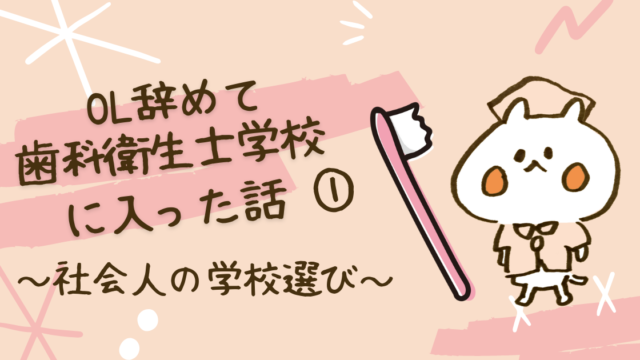医療係の資格で、学校に行かなくても取れるものは?
仕事しながらでも取りやすい資格を知りたい
今回は、医療の分野で就職や転職を考えていて、何か資格を取りたいと考えている方に向けた記事です。
筆者の私自身、医療関係の資格を2つもち、実際に医療現場で働いていた経験があります。
持っている資格のうち1つは、「医療事務」の資格です。
医療事務の資格は自宅での学習のみで取得しています。
こちらの記事では、私が取得した「医療事務」の資格のように、学校に行かなくても取れる資格について解説していきます。
資格の中には、ある一定の受験資格をクリアしていないと受けられないものもあります。その辺りにも触れていきますね。
- 医療係の資格で、学校に行かなくても取れるものを知りたい
- 仕事しながらでも取りやすい資格を知りたい
- 受験資格不要(完全独学)で取得できる医療系の資格が知りたい
- 資格に対応した講座が知りたい
資格には国家資格と民間資格の2種類がある
医療関係の資格は、国家資格と民間資格の2つに分けられます。
まずはこの2つの違いをざっくり知っておきましょう。
医療系の国家資格は取得に最低3年かかる
国家資格は法律に基づいて、国によって全国一律の基準で認定される資格です。
国が定めた施設や組織によって試験が実施されます。
医療関係の資格の中でも受験条件が厳しいものは「国家資格」であることが多いです。
基本、学校で3年以上学ばなければ受験資格が得られません。
中には受験するための条件が厳しめの資格もあります。
例えば、助産師さん。
- 女性であること
- 看護師免許があること
- 助産師養成コースで1年以上学んでいること
これが、助産師資格受験のための条件です。
看護師免許の取得には、最短3年学校に通う必要があるので、助産師試験を受けられるまでに最短4年かかることになります。
また、医療系の国家資格はその職業に就くためには必須になる場合が多いです。
医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、鍼灸師、柔道整復師、薬剤師、視能訓練士など
民間資格は「学校に行かなくても取れる」ものもある
民間資格は、国家資格以外の資格のことです。
民間の団体や、企業が試験を実施します。
誰でも受けられるものから、ある一定の受験資格が必要なものまで様々です。
医療系の国家資格は基本的に学校に通わないと取得できないとお話ししました。
民間資格であれば、学校に行かなくても取れる「医療系」資格もあります。
なので、今回は「医療系の民間資格」のお話しがメインになります。
民間資格は必須でない場合もありますが、勉強することで仕事をする上で役立つものや、就職に有利になるものもあります。
医療事務、調剤事務、医師事務作業補助者、歯科助手、看護助手、臨床心理士、細胞検査士
中間ポジションの公的資格
資格サイトを見ていたら「公的資格」っていうのがあるけど、コレは何?
公的資格は、「省庁のお墨付き」の民間資格や検定のことです。
試験そのものは民間団体や公益法人が実施していますが、主に省庁や大臣が認定しています。
簡単に言うと、国家資格と民間資格の中間的な存在だと思ってもらえればOKです。
公的資格は、結構曖昧です。
法令上の明確な分類の定義はなく、資格の紹介をしているサイトによって若干違う場合もあります。
准看護師、登録販売者、介護職員初任者研修、ケアマネジャー
【本題】学校に行かなくても取得できる資格6選
近年、医療業界はますます需要が高まっていて、多くの人が医療関係でキャリアを作り安定して働きたい!!と考えています。
一方で、時間やお金の制約があり、大学や専門学校に通うことができない人は、医療系の資格を取得することは難しいと思われるかもしれません。
以下では、そのような資格について紹介していきますね。
- 医療事務
- 医師事務作業補助者
- 調剤薬局事務
- 看護助手
- 歯科助手
- 医薬品登録販売者
こちらの職業の資格は全て、学校に通うことなく通信講座や独学で取得できます。
注意としては、受験の条件に特定の講座の受講が必須な資格もあります。
通信講座も使いたくない方は「完全独学可」と書かれた資格を見るようにしてください。
医療事務
医療事務の仕事は、何となく知っている人も多いのではないでしょうか。
医療事務の職場は大学病院やクリニックなど様々です。
医療事務は、病院やクリニックに来院する患者さんに対して、受付や会計業務、電話対応を行います。
患者さんの対応がメインとなります。
患者対応以外にも、電子カルテの入力や、毎月決まった時期に診療報酬を請求する業務(レセプト業務)を行います。
主な仕事内容
- 受付
- 会計
- 保険請求処理(レセプト)
- 患者対応
- 医療スタッフのサポート
平均年収は333万円(ボリュームゾーンは311万以下)、パートアルバイトの平均時給は1089円くらいです。
地域や医院ごとに、お給料の差は大きく、地方より都市部が高めです。
※参考 求人ボックス
- 人と話すのが好き
- パソコン作業ができる
- 几帳面
- 数字に苦手意識がない
医療事務員としてキャリアを積んだら、リーダー職を目指し、最終的には事務長などの管理職を目指す道もあります。
管理職になると、年収400万〜600万が目安になります。
総務課のある病院であれば、病院内の人事や経理担当として病院の経営を補佐するポジションもあります。
レセプト経験や事務経験を活かして調剤薬局事務や、一般事務にチャレンジしてみるのもありです。
医療事務の資格の4種比較
- 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク(R))
- 医療事務認定実務者(R)試験
- 医療事務管理士(R)技能認定試験
- 診療報酬請求事務能力認定試験(難しめ)
医療事務の資格で、代表的なものはこの4つです。全て、完全独学でも取得可能です。
※横にスクロールできます
| メディカルクラーク | 医療事務認定実務者 | 医療事務管理士 | 診療報酬請求事務 | |
|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 毎月 | 毎月 | 毎月 | 年2回(7月、12月) |
| 試験費用 | 7700円 | 5000円(一般) | 7500円 | 9000円 |
| 合格率 | 60% | 60~80% | 60~70% | 30~40% |
| 受験資格 | 特になし | 特になし | 特になし | 特になし |
| 在宅受験可否 | 可 | 可 | 可 | 会場のみ |
| 試験形式 | 筆記(選択式) 実技(記述式、レセプト点検あり) |
マークシート (レセプト作成あり) |
マークシート (レセプト作成・点検あり) |
筆記(選択式) 実技(記述式、レセプト作成あり) |
| 対応通信講座 | ニチイ | ユーキャン | ソラスト(教材のみ) | ヒューマンアカデミー通信講座『診療報酬請求事務』 |
| 講座費用 | ¥47,850 | ¥44,000(ユーキャン)
¥47,300(ヒューマンアカデミー) |
¥17600(ソラスト)
¥107657/入学金込含む(大栄) |
¥64,900 |
| 勉強期間目安 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月~1年 |
| おすすめな人 | 病院・クリニックの医療事務希望 | クリニック受付医療事務、病院受付希望 | 入院施設のある病院の医療事務希望 | 高ステータスな医療事務を目指す レセプト特化資格が欲しい |
※2024年2月現在
※医療事務の講座は、どれも資格の受験に必須ではありません
一番右の「診療報酬請求事務能力認定試験」は医療事務系で最高峰の資格といわれています。
合格率が30〜40%と難しめなので、少しハードル高めの資格です。
医療事務の資格は就職する上で絶対に必要なわけではありません。
履歴書には書けませんが、↓のような医療事務が初めての人におすすめの本で、独学で勉強しておくのもアリです。
フルカラーでわかりやすく、私も持っていました。
医師事務作業補助者
医師事務作業補助者とは、医師の指示のもと、診断書や療情報提供書の文書作成代行、電子カルテの入力代行など、医師の事務作業を補助することで診療のサポートを行う仕事です。
働く施設や病院によっては、医療クラーク・ドクターズクラークなどとも呼ばれます。
受付やレセプト点検などを行う医療事務とは異なり、診察室に入り、医師の指示を受けながら文書などを作成するので、より医療現場に近い仕事です。
小さなクリニックよりも、医師が忙しくて、事務作業にまで手が回らないような大学病院や総合病院が主な職場です。
主な仕事内容
- 診断書や療情報提供書等、文書の作成代行
- 電子カルテの入力代行
- 行政対応
- 診療に関わるデータ管理
医師事務作業補助者の給与の公式なデータはなかったため、複数のサイトで調べた金額をお伝えします。
医師事務作業補助者の年収は、250万〜400万くらいが平均のようです。
医療事務同様、勤務先によっても差がつきやすいみたいです。
- 責任感が強い
- PCスキルがある
- 事務作業が得意
- コミュニケーションスキルが高い
- 国語力がある
経験を積んだのち、リーダーとして、管理者のサポートやスタッフの指導などを行う道があります。
その後、係長や主任となり、専門職として高度な業務に携わるケースもあります。
医師事務作業補助者の資格3種比較
- 認定医師秘書
- 医師事務作業補助者検定試験(ドクターズオフィスワークアシスト)(完全独学可)
- 医師事務作業補助者養成講座(ドクターアシストクラーク)
医師事務作業補助者の資格はいくつかありますが、実務経験なしでも受験出来る資格に絞ると、この3つが代表的です。
医師事務作業補助者については、資格を選ぶ上で、32時間以上の基礎研修がポイントとなります。
どういうことか、説明しますね。
資格を選ぶ上でのポイント!
医師事務補助者として働くには、資格は必須ではありません。
ただし、必要な研修が2つあります。
- 32時間以上の基礎研修
- 6か月の研修
このうち、6か月の研修は実際に勤務してから始まります。
32時間研修は、入職前・後どちらでもOKです。
仕事をはじめる前に32時間の研修を終わらせておけば、その旨を履歴書にも書けるし、先に知識が身につくメリットがあります。
なので、資格講座等を選ぶ際に、32時間の研修を網羅しているか?を目安に選ぶのもポイントです。
| 認定医師秘書 | ドクターズオフィスワークアシスト | ドクターアシストクラーク | |
|---|---|---|---|
| 実施時期 | 年4回(3,7,9,12月) | 年6回(奇数月) | 試験なし |
| 試験費用 | 8200円 | 7500円 | – |
| 合格率 | 80% | 60% | – |
| 受験資格 | 指定の講座受講終了者 または 実務経験者(詳細規定あり) |
特になし | 日本医療事務協会の受講者のみ |
| 在宅受験可否 | 可 | 可 | – |
| 試験形式 | 学科 実技 (医療文書作成あり) |
マークシート | 課題提出のみ |
| 対応通信講座 |
【ヒューマンアカデミー通信講座】 |
ソラスト(教材のみ) | 日本医療事務協会 |
| 講座費用 | 55000円 | 11000円(教材のみ) | 70400円 |
| 32時間研修クリア | 〇 | × | 〇 |
| 勉強期間目安 | 6か月 | 1ヶ月~ | 3ヵ月 |
| おすすめな人 | 就職サポートも受けたい人 | 時間・費用を極力抑えたい人 | 試験を受けずに資格が欲しい人 |
※2024年2月現在
講座は使わず本で勉強したい方は、↓から医師事務作業補助者におすすめの本を探してみましょう。
調剤薬局事務
調剤事務は、調剤薬局で処方箋の受付やレセコンの入力、医薬品の在庫管理・発注などを通じて薬剤師の業務をサポートします。
主な仕事内容
- 受付、会計
- 処方箋、患者情報入力
- レセプト
- 薬剤師のサポート
- 医薬品の管理
調剤薬局事務の平均年収は295万です。
パート、アルバイトの平均時給は1046円くらいです。
※参考 求人ボックス
- 人と話すのが好き
- パソコン作業ができる
- 薬に興味がある
- 几帳面
調剤薬局事務からのキャリアアップとしては、調剤薬局の店長や、エリアマネージャーなどへの昇進も目指せます。
また、事務経験を活かして一般事務や医療事務にチャレンジする道もあります。
調剤薬局事務の資格5種比較
調剤薬局事務の資格もたくさんあるのですが、代表的な物を紹介していきます!
- 調剤事務管理士(完全独学可)
- 医療保険調剤報酬専門士
- 調剤報酬請求事務専門士(完全独学可)
- 調剤薬局事務検定試験
- 調剤報酬請求事務技能認定
調剤薬局事務の資格も、たくさんあるので迷ってしまいますよね。
※横にスクロールできます
| 調剤事務管理士 | 医療保険調剤報酬事務士 | 調剤薬局事務検定試験 | 調剤報酬請求事務専門士 | 調剤報酬請求事務技能認定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | 毎月 | 受講終了時 | 毎月 | 年2回(7,12月) | 受講終了時 |
| 試験費用 | ¥6,500 | 初回は講座費用に含む | ¥4,950 | ¥5280~17710 (級や併願による) |
認定料¥3000 |
| 合格率 | 60% | 80~90% | 非公開 | 1級20% 2級30~40% 3級50~60% |
非公開 |
| 受験資格 | 特になし | 指定の講座の受講者 | 指定講座の受講者 | 特になし | 指定の講座の受講者 |
| 在宅受験可否 | 可 | 可 | 可 | 可 ※通信受験:FAX(NTT回線のみ)が使える場合のみ |
可 |
| 試験形式 | マークシート |
非公開 (2択問題?) |
マークシート |
マークシート (1級は手書きあり) |
学科(三肢択一)
実技(レセプトの作成・点検) |
| 対応通信講座 | ソラスト(教材のみ) | 医療保険学院 | 日本医療事務協会 | 公式テキスト | ニチイ |
| 講座費用 | ¥8800 (ソラスト 教材のみ) |
¥19800 (医療保険学院) ¥42900 |
¥41800(通学) ¥32780(通信) |
¥2750~ (公式テキスト等あり) |
¥45049(通学) ¥36667(通信) |
| 勉強期間目安 | 3~4ヵ月 | 2~3ヵ月 | 通学3日~1ヵ月
通信1~3ヵ月 |
6ヵ月 | 通学1~2ヵ月
通信3ヵ月 |
| おすすめな人 | 独学で勉強したい人 | WEB講座で安く資格が取りたい | とにかく短期間で資格が欲しい | 調剤事務のエキスパートを目指したい人 | 就職サポートも受けたい人 |
※2024年2月現在
ちなみに、調剤報酬請求事務専門士の1級は調剤薬局事務でもっとも難しい資格といえます。
公式サイトではそれぞれのレベルをこのように例えています。
1級・・・リーダーレベル
2級・・・中堅社員レベル
3級・・・新入社員レベル
調剤薬局事務も資格が絶対に必要なわけではありません。
履歴書には書けませんが、↓のような調剤薬局事務が初めての人におすすめの本で、独学で勉強しておくのもアリです。
看護助手
看護助手は病院やクリニック、介護施設などで看護師のサポートをするのが仕事です。
ナースエイドや看護補助者と呼ばれることもあります。
仕事内容は、働く医療機関や部署などによって、多少任せられる業務の範囲が異なる場合もあります。
小さなクリニックや診療所では、受付業務を兼任することもあります。
主な仕事内容
病棟の場合は、入院患者さんの身の回りのお世話がメインになります。
- 入浴・排泄・食事介助など
- 病室の清掃・ベットメイキング
- 検査の付き添い
外来での主な仕事は、通院患者さんが処置を受けるための環境整備や患者対応です。
- 診察室等の環境整備
- 医療器具、備品管理
- 検査時のサポート
その他、オペ室配属ならオペ準備や手術台の清掃、透析室配属なら透析器具の準備や片付けなど、担当部門によって任される仕事は変化します。
看護助手の平均年収は342万円で、ボリュームゾーンは279~342万円です。
アルバイトやパートの平均時給は1215円です。
もっとも平均年収が高いのは関東でした。
※参考 求人ボックス
- 人と話すのが好き
- 体力がある
- 小さな変化によく気付く
- 自発的に動ける
看護助手自体には残念ながら明確なキャリアプランがあるわけではありません。
もちろん、歳をとっても働き口は多い職種なので、そういった意味では将来性はあります。
もっとキャリアアップ形成を意識したいと考えるのであれば、国家資格である看護師や介護福祉士にチャレンジする道もあります。
実際に看護助手を経験してから、介護福祉士や看護師に挑戦される方は多いようです。
看護助手の資格2種比較
- 看護助手認定実務者試験(完全独学可)
- メディカルケアワーカー
| 看護助手認定実務者試験 | メディカルケアワーカー | |
|---|---|---|
| 実施時期 | 年4回(3,6,9,12月) | 年3回(3,7,12月) ※1級は7月、12月のみ |
| 試験費用 | ¥3000 (ヒューマンアカデミー/認定料) ¥5000(一般) |
¥7700(2級) ¥8700(1級) |
| 合格率 | 60~80% | 2級72.7%
1級75.8% |
| 受験資格 | 特になし | 1年以上の実務経験者 または 指定の講座の受講者 ※1級は2級合格者 |
| 在宅受験可否 | 可 | 可 |
| 試験形式 | マークシート | 文章作成あり |
| 対応通信講座 | ヒューマンアカデミー通信講座『看護助手』 |
TERADA医療福祉カレッジ |
| 講座費用 | ¥46,200 | ¥39,000 |
| 勉強期間目安 | 3ヵ月 | 3~4ヵ月 |
※2024年2月現在
ヒューマンアカデミー(通信講座)経由のメリットは、試験を受験しなくても、修了試験に合格すれば看護助手認定実務者の資格が認定されること。
看護助手実務能力認定試験には、公式のテキストがあり、独学も可能です。
最も費用を抑えるなら、テキストだけ買って独学するのが良いといえます。
個人的な意見としては、就職後に必要なら、資格を取ることを検討しても遅くないと思います。
まずは、看護助手向けの本で学ぶのでも充分です。
歯科助手
歯科助手の勤務先は、ほとんどが歯科診療所です。
歯科医師や歯科衛生士の治療中のサポート以外にも、受付や会計などの窓口業務を兼任することが多いです
- 診療のアシスタント
- 器具の準備や洗浄
- 受付や会計
- レセプト
- 患者対応
歯科助手の仕事の平均年収は約336万円。ボリュームが多いのは309〜399万円です。
アルバイト・パートの平均時給は1094円です。
地域別でも差があり、関東が最も高めです。
※参考 求人ボックス
- 人と話すのが好き
- 貢献心が強い
- 世話好き
- 細かい作業が好き
- じっとしているより動きたい
歯科助手のままで大幅なキャリアアップは難しいかもしれませんが、より好待遇なクリニックへ転職する、事務長を目指すなどの方法で年収を上げることは可能です。
歯科での仕事を極めたい、より専門的なスキルを身に着けたいのであれば、国家資格である歯科衛生士にチャレンジする道もあります。
歯科助手の資格4種比較
- 歯科助手実務者
- 歯科助手専門員
- 保険請求事務技能検定試験(歯科)
- 歯科医療事務管理士(完全独学可)
歯科助手検定試験廃止
※横にスクロールできます
| 歯科助手実務者 | 歯科助手専門員 | 保険請求事務技能検定試験(歯科) | 歯科医療事務管理士 | |
|---|---|---|---|---|
| 実施時期 | – | – | 毎月 | 年6回 (奇数月) |
| 試験費用 | – | – | ¥7,700 | ¥7,500 |
| 合格率 | 非公開 | 非公開 | 93.50% | 70% |
| 受験資格 | 指定の講座の受講者 | 指定の講座の受講者 | 指定の講座の受講者 | 特になし |
| 在宅受験可否 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 試験形式 | 課題提出で基準に達すれば合格 | 課題提出で基準に達すれば合格 | 正誤問題、計算問題等あり | マークシート、レセプト作成 |
| 対応通信講座 | ユーキャン | 【ヒューマンアカデミー通信講座】 |
日本医療事務協会 | ソラスト(教材のみ) |
| 講座費用 | ¥34,540 | ¥49,500 | ¥55,000 | ¥12100(教材のみ) |
| 勉強期間目安 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 1~3ヵ月 | 1〜4ヵ月 |
| おすすめな人 | 少ないテキストで効率よく学びたい 試験が不安 |
診療介助をしっかり学びたい 試験が不安 |
レセプトをしっかり学びたい | 独学で勉強したい人 |
※2024年2月現在
歯科助手も資格が絶対に必要な仕事ではありません。
私的には、まずは歯科助手向けの本で勉強してみるのがおすすめです。
医薬品登録販売者
医薬品登録販売者とは、薬剤師に次ぐ医薬品販売の専門家です。
ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品(かぜ薬など)の販売ができる医薬品販売の専門資格です。
国家資格ではありませんが、公的資格と呼ばれ省庁のお墨付きの資格です。
ここまでに紹介してきた他の資格と異なり、登録販売者として働くには必ず資格が必要になります。
厳密には、1人で売り場に立てるようになるまでに1年以上の実務経験が必要です。(それまでは、研修中として就業可能)
- 薬選びのサポート
- 薬に関する情報提供
- 商品の品出しや陳列
- 在庫管理や発注
- レジ打ち
登録販売者の仕事の平均年収は約318万円。
ボリュームが多いのは296〜357万円です。アルバイト・パートの平均時給は982円です。
地域別で比較すると最も平均年収が高い地方は関西です。
※参考 求人ボックス
- コミュニケーション力が高い
- 健康に関心がある
- 新情報をアップデートできる
- 体力がある
登録販売者として医薬品への知識のみならず、店舗運営の能力も伸ばすことができれば、店長や複数店舗を管理するエリアマネージャーを目指すことも可能です。
更に大手ドラッグストアであれば、スーパーバイザー(マネジメント担当)や仕入れ担当など、本部の仕事に携わる道もあります。
医薬品登録販売者の資格試験(最低限知っておきたい情報)
資格試験で最低限知っておきたい情報をまとめました!
| 実施時期 | 年1回(8月下旬~12月中旬) 都道府県で実施日が異なる |
| 受験資格 | 特になし |
| 受験料 | 12800~18200円※都道府県で異なる |
| 試験形式 | マークシート方式 |
| 在宅受験 | 不可 |
| 合格率 | 約40~50% |
※2024年2月現在
医薬品登録販売者の通信講座の種類
医薬品登録販売者の資格は1種類だけですが、対応の通信講座はいくつかあります。
医薬品登録販売者の資格に対応した主な通信講座をざっくり比較します!
※横にスクロールできます
| 講座費用 | 学習期間 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| ユーキャン | ¥49,000 | 6ヵ月 | 受講開始から14ヵ月まで指導 |
| ヒューマンアカデミー通信講座『登録販売者』 |
¥47,300 | 6ヵ月 | 18ヵ月サポートで受講中最大2回試験にチャレンジ可 |
| オンスク |
¥1,628~(月額) | 1ヵ月~ | スマホメインで学習できる ※月額定額で受講し放題 ※1年勉強しても¥15,400と破格 |
| キャリカレ | ¥54,800 | 3ヵ月 | 不合格時の全額返金サービスあり |
※2024年2月現在
医薬品登録販売者の受験資格は特にないので、完全独学でも受験は可能です。
通信講座は使わず、本で勉強したい人ようにレビュー高めの本を紹介しておきますね。
資格の勉強は独学派?通信講座派?自分に合うのはどっち?
資格の勉強をしよう!と思ったら、次に迷うのが勉強の仕方ですよね。
それぞれ、メリットデメリットはあると思いますが、自分に合った勉強方法を選びましょう。
※一部の資格は、特定の通信講座の受講が必須なものもあります。(詳細は資格ごとの比較表をみてね)
| 独学 | 通信 | 通学 | |
|---|---|---|---|
| メリット | 費用が安い マイペースでOK 勉強したい部分だけ学べる |
マイペースでOK 効率よく学べる(時短) 添削あり、質問できる 就職サポートがある |
やる気維持しやすい 効率よく学べる(時短) 対面で質問できる 就職サポートがある |
| デメリット | 自己管理が難しい 最新情報が手に入りにくい 質問できない 自分で教材選定が必要 |
独学より費用が高い モチベーション維持が難しい 対面のやりとりはできない |
費用が高い 移動が必要 時間が取られる |
自分に合った勉強方法がわからない人は、以下のチャートも参考にしてみてください。

1人じゃ勉強のモチベーションが続かない人には、通学講座という方法もあります。
但し、通信講座や独学より高額になりがちなので、本当に必要かよく検討しましょう。
医療関係で働くメリットは?
転職・就職を考える中で、医療関係を選択する人は多いですよね。
人気なのは、医療系の仕事で働く魅力があるからだと思います。
医療関係で働くメリットを見ていきましょう!
医療職は「役に立っている実感を得やすい」
医療従事者になると、困っている人・弱っている人を手助けする機会は必然的に増えます。
更に、直接的に患者さんやお客様に関わる事も多いです。
直接「ありがとう」と感謝の言葉をもらえることもあるので、「役に立っている実感を得やすい」のが医療の仕事の大きなメリットですね。
病気だった患者さんが元気になっていく姿など、感動する場面に出会えることもあるかもしれません。
需要がなくならない、「安心感」がある
病院や薬がいらなくなる時代がくれば、話は別ですが・・・
医療自体がいらなくなることは考えにくいので、医療従事者が不要になることもないでしょう。
高齢化が進んでいることや、医療機関は景気の影響を受けにくいことからも、雇用が安定した業界と言えます。
「専門性が身につく」ので、復職・転職がしやすい
医療系の仕事は、一度しっかりと経験すれば専門性が身に付きます。
知識やスキルを身につければ、転職して職場を変えても即戦力として活躍することができます。
ブランクがあっても経験者は歓迎されやすいので、例えば結婚や出産で一度やめても復職しやすいメリットもあります。
ぶっちゃけ潰しが効くのはどの資格?
結論、医療関係の資格で潰しが効くものはないと思ったほうがいいです。
何故かというと、専門性が高いからです。
その仕事をするからこそ、意味をなす資格です。
全く関係ない業界に転職したくなった場合まで考えると、潰しが効くとはいえません。
強いて言うなら、医療事務や調剤事務などのレセプト系なら、まだ潰しが効くかもしれません。
ただ、同じ業界で移動する場合も、資格より経験をアピールする方が得策ではあります。
医療業界は民間資格の場合、経験のほうが物を言う世界です。
汎用性が高い資格が欲しいなら、PCスキル系(Excelなど)の勉強をしたほうが、理にかなっています。
民間資格は「意味がない」って本当?
資格について色々調べていると、民間資格は意味ないって意見も見かけます。
- 希望の就職先の応募条件に含まれる
- 資格を取ることでお給料が上がる
- ゴールがあるほうが勉強しやすい
- 既に同分野の国家資格を持っている
- 実務経験が豊富で今更感がある
- 10年以上前に取った資格
筆者自身は、医療事務の仕事をしたことがありますが、資格は転職後に取りました。
だから、資格を取る意味はあったと思います。
でも、資格を取る・取らないに関係なく勉強はしたほうが、仕事が覚えやすいのは確かです。
一から手取り足取り教えてくれる現場は中々少ないですし。
どうせ勉強するなら、勉強した証を形に残したい人や、履歴書に書けるものが欲しい人は資格にチャレンジしたらよいと思います。
実際のところ資格があったほうが、就職に有利?
医療業界自体未経験の人で、受付やレセプトを担当するようなポジション希望の場合は、資格を持っているか?は一つの判断材料にされているように思います。
採用する側は、窓口業務や請求業務で必要な最低限の知識は持っていて欲しいと思っています。
保険制度やレセプトの考え方は全国共通なので、資格の勉強をするとある程度頭に入ります。
なので、資格あり=最低限知識ありと判断してもらいやすくなると思うんです。
逆に、受付やレセプトはなしで補助業務メインに応募するなら、資格は重要視されないかもしれません。
学校に行かなくても取れる医療系の資格 まとめ
今回は、学校に行かなくても取れる医療系の資格についてお伝えしました。
興味のある資格はみつかりましたでしょうか?
- 医療事務
- 医師事務作業補助者
- 調剤薬局事務
- 看護助手
- 歯科助手
- 医薬品登録販売者
気になるものがあれば、資料を取り寄せて手元で見比べてみると自分に合うものを見つけやすいですよ。
資格取得最大のメリットは自信に繋がることですよね。
今回、資格を調べてこの記事を読んでるだけでも、「学び続けられる人」の素質があると思います。
(そこまで調べない人の方が多数ですよね)
今回紹介した資格は必ずしも必要ではないですが、上手く利用して仕事や就職に役立てられますように。